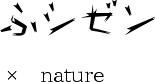前回のつづき。
瀧泉寺(目黒不動尊)の最寄の駅は、
・ 目黒
・ 不動前 ・・・ 東急目黒線
バスは五反田駅から。
不動前駅から
・ 不動前駅通り商店街
・ 目黒不動商店街(不動尊参道)
山手通りに不動尊参道バス停。大崎駅、中目黒駅などから。
八ツ目や にしむら ・・・ うなぎの名店
- 不動前駅/不動前駅通り商店街 - かむろ坂 - 目黒不動商店街 - 目黒不動尊
目黒駅からは行人坂(急坂)を下って、太鼓橋を渡って、山手通り。
そのまま直進すると蟠龍寺(蟠竜寺、岩屋弁天)。
山手七福神の弁財天を祀っている。
- 太鼓橋 - 蟠龍寺
- 大鳥神社 - 蟠龍寺 - 五百羅漢寺 - 目黒不動尊
五百羅漢寺(rakan.or.jp/)
「目黒のらかんさん」
目黒不動尊
大鳥神社、目黒寄生虫館に立ち寄ったので、北側の不動公園から目黒不動尊へ。
- 目黒寄生虫館 - 目黒不動尊
なぜかいつも裏手から。

甘藷(かんしょ)先生=青木昆陽の墓。
徳川吉宗の時代、18世紀、享保の大飢饉-享保の改革で、甘藷(サツマイモ)の栽培を広めた先生(蘭学者)。
▼ 大本堂
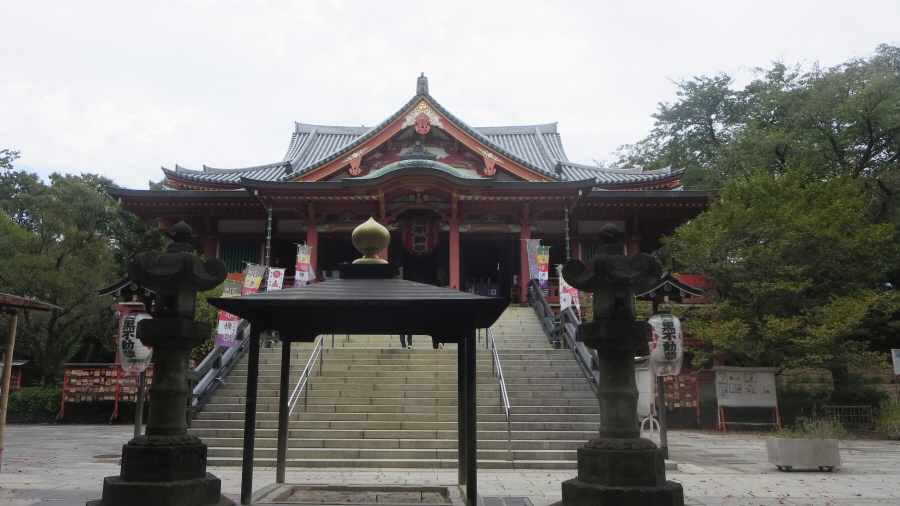
瀧泉寺(滝泉寺、目黒不動尊)
・ 公式HP(megurofudo.jp/)
・ MEGURO FUDO LOVE(目黒不動尊LOVE)(megurofudo.love/)
毎月28日に縁日
瀧泉寺は平安時代、808年、慈覚大師・円仁によって開山。
本尊は不動明王(不動尊)。
目黒不動尊の名は江戸時代以降とされる。目黒や目白が五色不動(ないし三不動)として広く知られている。目赤、目青、目黄もあり、いずれも街道や上水の江戸入口に配されている。江戸城鎮護のため。
ただし、目青や目黄は後から付け加えられたとも言われる。
再び甘藷先生。救民偉人:青木昆陽の言葉。
『享保二十年 甘藷を種う 甘藷流傳して 天下をして飢うる人無からしむる 是れ予が願なり』
▼ 不動尊子供会のサツマイモ畑

青木昆陽さんの後、報徳農政:二宮尊徳さん。

万象具徳
『どんな ものにも よさがある
どんな ひとにも よさがある
よさが それぞれ みなちがう
……』
大本堂から階段(男坂)を下って、右手に独鈷の滝。
『長く不動行者の水垢離の道場として利用されてきた』
※ 独鈷(とっこ):密教の仏具。もと古代インドの武器
垢離(こり)、水垢離(みずごり):水を浴びて心身清めること

今は中に入って水浴びできないが、水かけ不動明王(下の写真右)に水を浴びせると身を清めたのと同じになる。

睨み利かせています。
▼ 国立国会図書館「錦絵でたのしむ江戸の名所」から歌川国芳 目黒不動之図(www.ndl.go.jp/landmarks/details/detail419.html)

「錦絵でたのしむ江戸の名所」にて
歌川広重 江戸名所 目黒不動尊(www.ndl.go.jp/landmarks/details/detail421.html)
なども閲覧できる。
この地は古くから湧水地。
古代中国発祥の五行(ごぎょう)によると黒は水に相応するが、目黒という地名は江戸時代よりも前から存在する。
鎌倉時代の御家人・目黒氏は、この地の目黒に由来するという。
この点疑問に思っていたが、
徳川家光と僧・天海が五行によって不動尊5ヶ所を選び云々の説明は、少し差し引いてみる必要があるかもしれない。
ちなみに目黒の由来の有力説は、馬(め)畔(くろ) ⇒ 目黒とのこと。確かに周辺に馬や駒の付く地名が目に付く。
黒目がひっくり返った可能性もありそう。
帰る。

仁王門が入口。
道路に出て右手に滝見茶屋(瀧見茶屋)。
開運焼き芋、甘藷ぷりん、……。
バス乗り場。五反田駅方面と恵比寿駅・渋谷駅方面。
滝見茶屋の隣に池がある。

橋の先に
・ 金明(こんみょう)湧水 福銭洗い
・ 豊川稲荷
・ 三福堂
「えびす神」。山手七福神
恵比寿神、大黒天、弁財天合わせて三福神
山手七福神の残る四神(3寺)は目黒駅の東側
カメ(亀)達がわらわら寄って来た。

女坂の階段や比翼塚など見落とした所もある。
また来よう。
林試の森公園へ---。