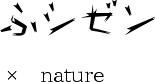初めて大阪訪れた時は大阪駅周辺、大阪城公園散策。
その後、訪れた時も大阪駅、大阪城周辺散策。
大阪の玄関口かつ一二の観光地(だと思う)。
大阪城(大坂城)
江戸時代までは大阪ではなく大坂で、歴史にまつわる話の中では大坂城など大坂表記が多い。
大阪城公園
大坂城(大阪城)
豊臣秀吉、築城 ・・・ 初代大坂城
1614年、大坂冬の陣~1615年、大坂夏の陣で落城。
徳川家康、再築 ・・・ 2代目大坂城
1665年、落雷で天守閣焼失。再建されず。
現在の天守閣は3代目。1931年(昭和6年)完成。
天守閣の高さ(天守台含む)約55m。
現存および復元されている天守閣の中では最も高い。
2025年4月、豊臣石垣館OPEN。地下にある初代大坂城の石垣を展示。
大坂城の石垣の大石は瀬戸内海の島々からも運ばれた。
使われずに放置された大石は「残念石」。
- 大阪城公園(osakacastlepark.jp/)
- 大阪城天守閣(www.osakacastle.net/)
- 大阪城観光ガイド(osaka-castle.jp/)
本丸広場にMIRAIZA OSAKA-JO(ミライザ大阪城)。
以前は大阪市立博物館。
▼ 北西、京橋口から天守閣

大阪城御座船(ござぶね)
北、極楽橋から内堀めぐり
極楽橋の近く、青屋門
その近く、大阪城ホール
- 京橋口 - 極楽橋 - 青屋門 - 玉造口、豊国神社 - 桜門 - 大手門
- 極楽橋 - 天守閣、本丸広場 - 桜門
大手門から西の丸庭園
大阪迎賓館など
アクセスは、
・ 天満橋駅 - 京橋口
・ 大阪城北詰駅 - 大阪ビジネスパーク駅 - 青屋門
・ 大阪城公園駅 - 青屋門、玉造口
・ 森ノ宮駅 - 玉造口
・ 谷町四丁目駅 - 大手門
極楽橋~大阪城公園駅~森ノ宮駅をロードトレイン、
南外堀の周りをエレクトリックカー
が運行。
大坂城築城前は一向宗(浄土真宗)の石山本願寺(大坂本願寺、大坂御坊)。
織田信長と長期に及ぶ石山合戦 [1570年-1580年]。
寺といっても強固な城塞だったようで、1580年に講和。
驚き。
一向宗の拠点になる前は大坂ではなく小坂だった。逢坂に由来するのかと思っていたが、別のよう。
大阪(おおさか)はもと小坂(おさか)だった。
大手前、大手通、本町橋、…
大阪府庁舎本館
大阪歴史博物館
マイドームおおさか
・
・
・
天満橋駅
八軒家浜港(川の駅はちけんや)(8ken-ya.osaka/)
水上バス(クルーズ)の主要発着場の1つ
天満橋~天神橋に「渡辺津」の記念碑。中世・大坂(大阪)の港。今は旧淀川(大川)。
熊野詣の起点。「窪津」とも。
古代は一大港・難波津。
難波宮跡
大阪は奈良・京都に比べて古都のイメージが薄いが、飛鳥時代~奈良時代、「都」だったことがある。
大阪城の南の難波宮(なにわのみや)跡[公園]。古の「大阪都」、日本の都。難波津から瀬戸内海~西国とつながっていた。
昔、古の「都」に関心抱いて、奈良の平城宮跡とともに難波宮跡に立ち寄った。どちらも閑散とした広場だった。
今はどちらも整備されて訪れる人が増えているよう。
- 谷町四丁目駅 - 難波宮跡公園 - 森ノ宮駅
後期難波宮は奈良時代、聖武天皇の時代。
8世紀。744年の1年弱。
前期難波宮は飛鳥時代、孝徳天皇の時代。難波長柄豊碕宮。
7世紀。乙巳の変(大化改新の政変)の後、飛鳥(奈良県明日香)から都が遷った。
短期間(650年-654年)で都は再び飛鳥に遷ったが、遷った後も副都的存在。686年に焼失。
▼ 難波宮跡公園

後期難波宮跡の大極殿(だいごくでん)の基壇が復元されている。登壇、休憩。
道路(中央大通、阪神高速)の向こうも難波宮跡。北部ブロック。
※ 阪神高速が公園のところで高架から地上へ下りてくる。高架だと(埋まっている可能性が高い)遺跡が破壊されてしまう可能性があるため
後方左が大阪歴史博物館、その左隣の高いビルはNHK。
博物館の右は大阪府農林会館(今はない。大阪農林会館とは別)。跡地に商業施設「なノにわ」(naniwanomiya.jp/)。2025年3月OPEN。
なにわのみや1400 PROJECT(naniwanomiya1400.com/)
2050年が遷都1400年。
古墳時代も大阪に都が置かれたことがある。
仁徳天皇の時代、難波高津宮(たかつのみや)。
今日、上本町の西に高津宮(こうづぐう)が鎮座しているが、元は(今日の)大阪城付近にあったとされる。
未発見なので推定の域を出ないが、(今日の)難波宮跡から5世紀後半の巨大倉庫群が発掘されている。大阪歴史博物館にある法円坂遺跡(法円坂倉庫群)。
昔は現在よりももっと海に近かった。
大阪歴史博物館(www.osakamushis.jp/)
愛称「なにわ歴博」
仁徳天皇の時代は(おそらく)5世紀頃。
国内最大の前方後円墳・大山古墳(堺市)が伝・仁徳天皇陵で、こちらも5世紀頃。被葬者は仁徳天皇もしくはその子(履中天皇、反正天皇)とみられる。
ついでながら上本町の西にある生國魂神社(難波大社)も(今日の)大阪城付近にあったとされる大阪最古の神社。神武天皇の時代創建。
生玉(いくたま)とか、生駒(いこま)山とか、神武天皇よりも一足先に「天磐船」に乗ってやって来たというニギハヤヒノミコト(邇芸速日命、饒速日命)と関係深そう。
飛鳥時代に話を戻すと
難波宮から南へ難波大道(なにわだいどう)が造られて大和・飛鳥方面と結ばれていた。
難波宮造営前の7世紀前半からなので、一大港・難波津からの大道。日本最古の官道。
宮(宮殿)の周りに碁盤目状の本格的な京(都)が造られ始めたのは7世紀後半の「藤原京」(飛鳥の北、奈良県橿原)とされている。
その前の飛鳥や難波も飛鳥京、難波京と呼ばれることがあるが、飛鳥には碁盤目状の京(都)はなさそう。
難波と九州・大宰府が「藤原京」より先んじている可能性あるのでは、と考えたことあるが、不詳。
森ノ宮~玉造
森ノ宮駅
鵲森宮(森之宮神社)
もりのみやキューズモールBASE
かつて日生球場
玉造稲荷神社
伊勢本街道の起点
玉造駅
真田山公園
玉造駅の西、真田山公園の北に大坂冬の陣で知られる出城「真田丸」が築かれた。
大阪城東部地区まちづくり
JR大阪城公園駅の東、「森之宮」地区に新駅(森之宮新駅)建設予定
森ノ宮駅から大阪メトロ延伸
駅ビル、アリーナ・ホールなど
2028年OPEN予定
現在、大阪公立大学キャンパス建設中
2025年OPEN予定
大まかにみると天満橋、難波宮跡~四天王寺が熊野街道や難波大道のルート。
大阪・兵庫にまたがる摂津(せっつ)国の国府推定地も天王寺周辺や難波宮跡。
古代まで遡ると現在とは大きく異なる地形で、
歴史好きには興味そそられる一帯だと思う。